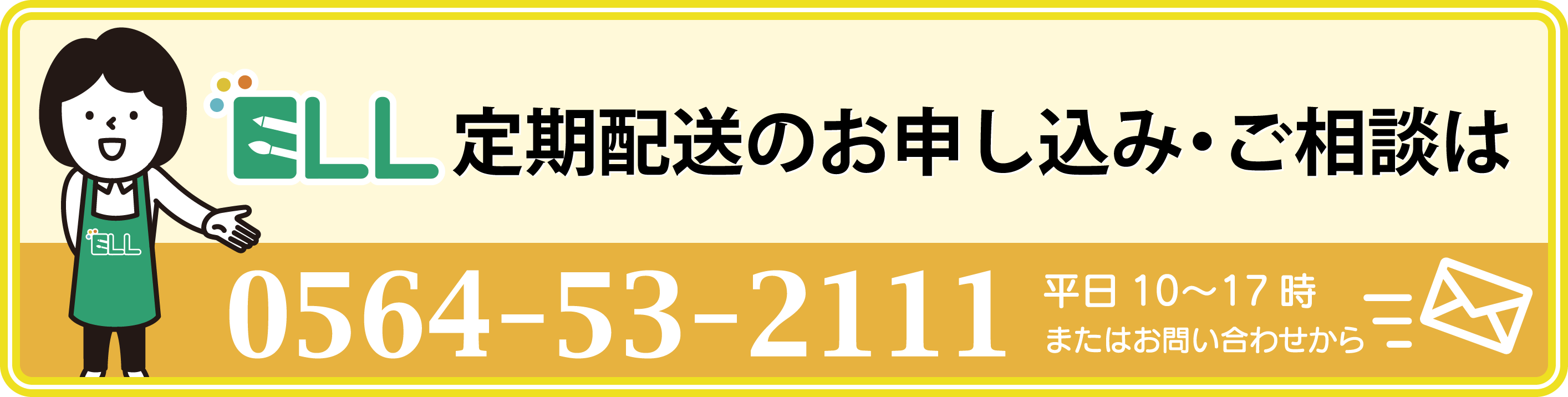- 介護レク作品キットELL
- テーマ『革ストラップ』に関するトピックス
アクセサリー『革ストラップ』のトピックス
“1,000年以上の歴史「日本の革文化」”
記録に残る日本で最古の皮『亜久利加波』
日本で記録に残っている最古の皮は、古墳時代(3世紀中頃〜7世紀頃)の『亜久利加波(あくりかわ)』といわれています。
亜久利加波は、皮についた脂を取り除いただけの毛皮で、なめし等の加工がされていない原皮でした。このときの大和朝廷の税として、男性には『弓弭調(ゆはずのみつぎ) =狩猟による獲物』を女性には『手末調 (たなすえのみつぎ)=麻・木綿などの布、絹織物』を貢納させたと記されています。
革の加工技術をもたらした『渡来人』
日本に革の加工技術が伝来したのは、聖徳太子が生きた飛鳥時代(593〜710年)に中国や朝鮮半島などから日本に移住した人々「渡来人」よるものだと言われています。
当時は、丈夫でしなやかな鹿の革が使われていました。そして、その特徴を活かし、貴重だった鉄に変わる素材として、甲冑や鎧などの武具、馬の鞍など様々な生活用品に用いられました。

株式会社日研
〒444‐0825
愛知県岡崎市福岡町井ノ元5番地
0564-53-2111
〒444‐0825
愛知県岡崎市福岡町井ノ元5番地
0564-53-2111
株式会社日研
〒444‐0825
愛知県岡崎市福岡町井ノ元5番地
0564-53-2111
〒444‐0825
愛知県岡崎市福岡町井ノ元5番地
0564-53-2111